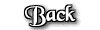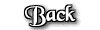田川の改修
■今の田川隧道
山中の隧道を通って五十嵐川に注ぐところ 平成11年10月
月ヶ岡養護学校のすぐ近くに田川の水は吐き出される。
先生の遺志を受け継いだ人々の働きがあった。明治19年(1886)、病に伏していた松尾は
自らの死期を悟り、懇意にしていた新保村の大桃大五郎を招いて、四日町を水害で悩ませる月岡村
山中より流れ出る田川の氾濫を治めるために、月岡の山を切り崩し、悪水を五十嵐川に流すように
頼むと、その3日後である同年3月15日に亡くなった。
[参考文献/「松尾与十郎」三条市歴史民俗産業資料館]
■隧道の注入口
運動公園近く ここから地下を通って五十嵐川に 平成11年10月
与十郎が最後まで気にかけていた田川である。
明治21年(1898)年に北越鉄道が敷かれた際に、
田川の排水を整えることは鉄道線路を守る事でもあると、大桃大五郎(新保)、金子禄三郎(新保)、高橋平造(四日町)、小林林蔵(四日町)、佐藤善米(四日町)、角田与五平(諏訪)、山倉定七(月岡)らが北越鉄道から随道工事費として2500円を提供させた。そのうち
1560円は墜道工事費に、940円は用水路樋管などにあて、明治34年(1901)5月に竣工した。
隧道の長さはおよそ550メートルである。
[出典/「松尾与十郎」三条市歴史民俗産業資料館]
栄町吉野屋山中から月岡に向かう田川 平成11年10月
粘土質の山々なので、大雨になると粘土に水を入れてかき回したような、ごっとんごっとんした水が
流れるそうである。
[大箭耕七氏談]
■かつての田川隧道
昔の田川隧道 今は柵がしてある 平成11年10月
古い隧道は手彫りであったので、中は段差があり、すんなりと水が流れずよどむ場所があったそうである。中を通った人が
あまりの段差に驚いたという。昔の技術では、難しい工事であった。
[大箭耕七氏談]