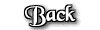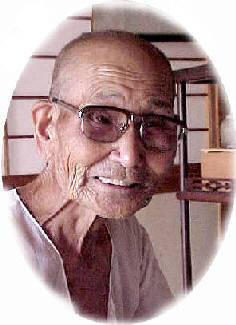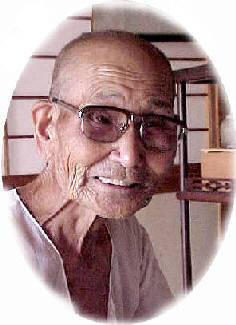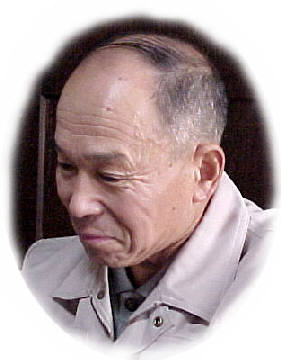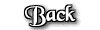地域の皆さんに話をうかがいました
■諏訪精一様 (片口、平成13年2月ご逝去)
平成11年10月撮影
[生まれ]
明治43年生まれ
[松尾様の屋敷]
諏訪精一様は、松尾宅の跡に、住んでおられた。
松尾は屋敷が7反ぐらいの土地があったらしい。現在は3反である。敷地内には直径が1mもある大きな「松尾様の石」が多数ある。五十嵐川から運んだものらしい。
[稲荷様]
諏訪様は松尾の戒名を光照寺住職から書いてもらい、自分の仏壇に奉っておられる。松尾の頃には、稲荷様が屋敷にあった。現在は、諏訪神社(電力住宅跡地にあった)と合わせて、3つの神様を片口鎮守様として白山様に合祀してある。
[当時の建物]
長屋門の一部が残っている。もともとは1階建てであった。中も白壁が塗られていたそうだ。
昭和60年の100年祭の時、四日町小学校で式典をやったが、その時に光照寺にある墓を直した。その後は、みんな年をとり、法要を行う方もいなくなってしまった。
[片口村]
片口は水をかぶる心配は全くなかった。大正15年の水害でも松尾跡屋敷だけは水が入ってこなかった。ダムができてから水害の心配はなくなった。
■大箭耕七様 (片口)

平成11年10月撮影
[生まれ]
明治44年生まれ
[松尾家の由緒]
「信州のさる大名の家来だが、故あって来越し」(常磐橋の松尾銅像の看板)とあり、その理由を調べた。「徳川系譜」という書物から考えると、福島正則(岡山県)の家来ではなかったか、と推測される。福島は岡山49万8千石であったが、長野へ移封され4万5千石となる。息子も正則も殺されたが、(「水の砦」という本か?)その後は2万石、そして3千石に減封されてしまう。家来を養うことができない状況となり、松尾も浪人となったのではないかと、考える。岡山や長野の図書館に福島の家来に「松尾」という姓がいないか調べてもらったが、いなかった。正式の武士ではなく「土の者」「草の者」といわれるような存在だったのではないか。
[石動法師と松尾]
吉野屋の「松尾屋敷」の脇に石川県の石動法師たちのたまり場があったそうだ。法師は、諸国を回りながら、指圧や骨接ぎやなどをする人たちであった。松尾の祖先は、その人たちと一緒に長野から来たのではないか。石動法師たちのたまり場の隣に屋敷を構えたのはそのような理由と考えられる。法師たちの中には、たまり場の前を馬に乗って通る人があると、気合いをかける者がおり、驚いた馬から転落しケガをする者が出たそうである。村では、ここにたまり場があることは困るということで、山の上に移ってもらった。山の上にある現在の石動神社である。地域の人々は、この神様は何でもかなえる不思議な力があることから「権現様」と呼んでいた。
[築堤の理由]
母親(金子新田)や妻の実家(袋)が信濃川が洪水になると水浸しになる地域であった。この姿を見て感じることもあったろうが、一番の理由は地租改正であろう。これは、それまでの収穫に対する税ではなく地価に対する税であり、しかも金納であったので、毎年同じくらいの米を収穫しなければ百姓の暮らしは成り立たなくなる。松尾はそんな危機感を持っていたのではないか。土手を築いて洪水から守るより他はなかったと考えたのであろう。
[片口に来た理由]
松尾は、大面組の庄屋であった。長嶺山崎新田に「角田にざえもん」という人がいた。この人は、片口の米を集めて、三条陣屋へ米を納めていたが、茨城の方へ移ってしまった。その跡を継いだのが6代目の松尾記右エ門であった。
[金子新田や袋の水害]
金子新田や袋も昭和10年頃まで、長野で雨が降ると、信濃川の水があふれ、五十嵐川の水も逆流し、大変だった。大水が出た時は、夏なら田下駄等で歩けるが、春先の雪解けの時は寒くて大変だった。消防の分遣所の辺りから四日町までは、俵に土を入れたものが置かれ、その上を歩いたものである。大河津分水ができてもなお、こんな悲惨な状況であった。
[与十郎の学問]
北潟の塾へ通い、吉野屋へはよく行ったそうだ。
[肖像画]
鱈田校、吉田校、月岡校の運動場、本成寺役場(大正14年まで、三条高校の東側)の4カ所にあった。しかし、終戦の時に軍事色が強いのでは、という心配から処分した。現在のものは昭和60年の100周年祭の時に再度復元し配布したものである。本町の藤田カメラ点から復元してもらった。
[田川]
古い隧道は手彫りであったので、段差があり、すんなりと水が流れなかったそうである。粘土山なので、粘土に水を入れてかき回したようなごっとんごっとんした水であった。亡くなってから10年後にやっとできた。
長屋門とは、下男下女が寝泊まりしながら番もする門のことである。松尾の屋敷で残っているのは、この建物のみである。現在では、2階部分も増築され、かつての姿は、想像するしかない。
なお、昔はこの手前側に8畳間ぐらいの部屋があったそうで、お年寄りが住んでいたそうである。
■諏訪利三郎様 (片口)
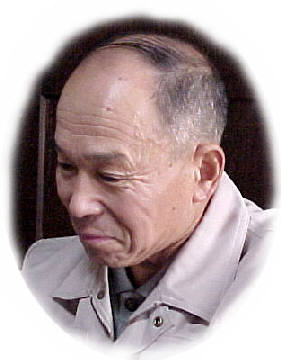
平成11年11月
[資料が多数ある理由]
諏訪さんは、現在片口の自治会長をされている。松尾家が傾いて、庄屋の仕事を継いだため、松尾家に関わる史料が多数保管されている。また、当家の蔵は、片口校で使っていた材木も使って作られている。
[偉大だったこと]
何といっても教育分野であった。私塾を開いて地域の子供たちに教育を行ったからである。当時の教科書が当家には残っている。片口校の出身者には諏訪伝次郎がいる。松栄橋を架ける時の願い人である。後に高根村(現岩船郡朝日村)の村長となった方である。片口校の費用は、村の篤志家がお金を出し合って運営されていた。
[肖像画]
写真は、まだ写真が珍しい頃に、新潟で撮ったものである。それをもとに肖像画が描かれ、各校に配られた。松尾のことを教育で取り上げることは、困難に立ち向かっても、公益のために生きることは大切である、ということを知らせることにある。教材としてすばらしいのではないか。
[学問好き]
大面組には諸橋轍次(大漢和辞典の作者、父は大面出身)にもつながる豊かな学問の風土があった。松尾が学問好きであったことと、幼い頃この土地で学んだことは大いに関係があるのではないか。
[経済的基盤]
田圃は片口全体でも約12町歩である。そのうち松尾が所有していたのは約8町歩であった。松尾は自分で農耕に携わることはなかったのではないか。
[先祖]
吉野屋(栄町)から片口に移ってきた。吉野屋には、今でも地域の人々から「松尾屋敷」と呼ばれている場所がある。県道大面保内線沿いの石動神社の近くである。
[松栄橋]
外山整形外科の隣の小路が当時の四日町の幹線であり、当時のままの道幅である。したがって松栄橋は、現在の常磐橋より少し下流に架けられた。
■中澤禎壱様 (東本成寺 平成13年9月ご逝去))

平成11年12月
[中沢鶴居について]
中澤様は、中沢鶴居(たづい)氏のご子孫であり、鶴居氏の曾孫である。鶴居氏は、村々をまとめる小区長という立場であり、松尾の考えを支持し、最後まで行動をともにした人である。特に、明治5年に県令の平松時厚、大参事の南部信近らがこの地を訪れた時の堤防建設を訴える二人の連携はみごとであった。また、築堤に関しては、村々の協力を呼びかけることに奔走したり、工事中にも問題が起きると松尾と協力をして解決に当たったりした。松尾の人物像に迫るべく、貴重なお話が伝わっていらっしゃるのではないかと期待したが、時間という大きな壁が立ちはだかって、伺うことはできなかった。中沢さん自身、先祖が松尾と何らかの関係があることを知ったのは、100年祭の時に資料を求められて初めて分かったそうである。
[資料について]
当家には史料が多数あったが、市史編纂委員会や県へ出されたという。また、明治12年ごろ火事にあって、それ以前の貴重な史料はほとんど失われたという。
[東本成寺の堤防]
東本成寺の堤防の様子、とりわけ「輪中」について、詳しく話を聞くことができた。水害から村を守るために部落をぐるっと土手で囲んだ話である。その堤防上にはクルミが植えられ、子供の頃はクルミもぎをしなければならず、とても大変だったそうである。現在でもその名残があるというので、早速見に行った。