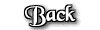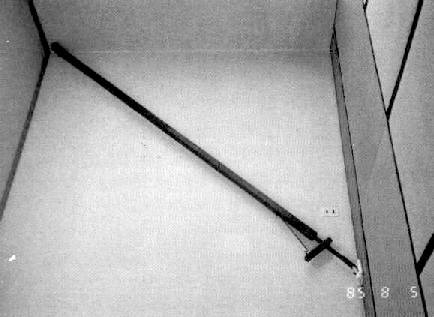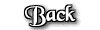松尾先生をしのぶ品々
■松尾家の仏壇
三条歴史民俗産業資料館蔵
三条市歴史民族産業資料館(鈴木喜久次館長)にこのほど三条の偉人、松尾與十郎の家の150年以上昔に作られた仏壇が寄付され、同資料館の近現代のコーナーに展示している。
三条市吉田、曹洞宗霊陰山西明寺の佐藤明臣住職が寄付した。仏壇は今の農家の仏壇と同じくらいの大きさで150代の高さ165 、幅124 、奥行き70。今となってみればシンプルな作りだが、当時は扉を開けると段があるだけがふつうだったのでそれと比べれば木彫などが施してある分、豪華なようだ。
三条新聞記事より
■松尾家仏壇の裏

三条歴史民俗産業資料館蔵
松尾家の仏壇だった証拠は背中にある。“天保八丙年十月日調之 松尾與右エ門正久 代金三両弍分 正匠三條町清松”と筆で書いてある。仏壇はさわるのも気がひけるくらいすすで真っ黒に汚れているが、裏は汚れが少なく、今でもはっきりと読み取ることができる。天保8年は西暦で1837年、松尾與右エ門は與十郎の父。與十郎は天保3年の生まれなので與十郎が5歳のときに與右エ門が求めたのだろう。清松は今の三条中央商店街駐車場裏の土手に住んだ戸大工。本来なら仏壇職人に作らせるところ、清松に頼んだということは二人が親しかったのではないかという推測を生んで興味深い。
また、仏壇内部は金箔が張ってあるように見えるところがあるが、仏壇店の話だと、これは金箔がなかなか手に入らなかった時代に銀箔の上にうるしを塗ると酸化して金のような色を発する手法を施してあるとのことで、その辺りにも興味をそそられる。(中略)
しかしそれがたたって家は傾き、與十郎が明治19年に55歳で死去してから11年後の三十年、遺族は東京へ移った。東京へ移るときに家財道具いっさいを処分した。この仏壇もそのうちのひとつ。三条市月岡の人が買い求め、家の仏壇として使っていたが、傷んできたので十年近く前に新しい仏壇に買い替えることにした。
仏壇を処分する前に仏壇から魂を抜き取る開眼戻しという法要を行うが、それを頼まれたのが佐藤住職。仏壇のいわれを聞いて三条の貴重な歴史資料であり、どうせ処分するのならとゆずってもらい、それをこのほど同資料館に寄付した。
三条新聞記事より
■自在鈎
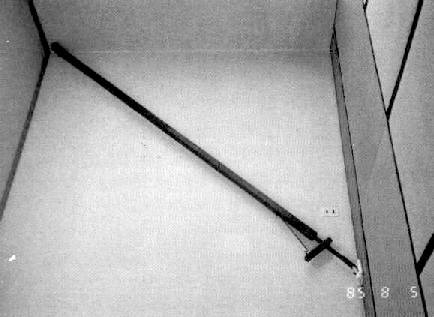
百年供養祭出版物より
松尾常用の自在鈎である。三条駅前の「みなとや」にある。
「みなとや」の創始者は、諏訪家(諏訪利三郎氏の3代前の頃)に作男として住み込みをしていた。そこで同じように働いていた女性と夫婦になり、三条駅前へ分家独立することになった。その時、世帯道具として、また汽車待ちの人にお茶を勧める湯を沸かす鉄瓶をかけるのに用いるようにと、諏訪家より送られたものである。使用しなくなって片付けられていたが、築堤100周年記念祭の時、出していただいた。(大箭耕七氏談)